本物は「伝統」ではなく「愛」
東京で生まれて育ったわたしは、お醤油は濃口、お味噌は米味噌が当たり前だった。濃口、薄口、白醤油という区別、米味噌、麦味噌、豆味噌と色々あること自体も正直最近まで知らなかった。だから、三河みりんなんて知らなかったし、八丁味噌がうちの冷蔵庫にストックされる日が来るなど思ってもみなかった。
白状すれば、八丁味噌や三河みりんの「三河」という土地に少々の偏見も持っていた。バブルの申し子、アメリカ礼賛、エリートホワイトカラーとして成功したいと思っていた20代、30代、40代だったから、三河に代表される自動車メーカーの経営方法がどうにも受け入れられず、「個より組織」「会社を支えるのは個人のパフォーマンスではなくてシステム」と言い切るその社員の方達に驚愕したし、わたしには無理だし、そもそもお互い相容れないと思っていた。
先日、okatteにしおぎや東北の「はっと」活動でご一緒する友人が、彼女の地元・岡崎の誇り「まるや八丁味噌」の浅井信太郎社長と一緒に三河の調味料作り手さん4社を訪問するツアーを企画してくれた。訪問を終えて、色々な出来事が腹落ちした今、それぞれの作り手さんの「ものづくりへの愛」を支えるのは、三河という人とモノを大切にする風土や気質なんだろうなと感じている。そして、三河という土地がとても好きになっている自分がいる。
Mr. Hatcho – まるや八丁味噌・浅井信太郎社長
家康公の岡崎城から西へ八丁。(870メートル)旧東海道を挟んで「まるや八丁味噌」と「カクキュー八丁味噌」がある。(余談:岡崎城は、昨年の大河「おんな城主 直虎」で、阿部サダヲ(家康)の「(桶狭間のどさくさに紛れて)戻れてしまったのう!」という怪演で初めて知った。)この日、浅井社長は他の作り手3社の見学を優先してくれて、まるや八丁味噌に到着したのは営業も終わった6時近くのことだった。美しい佇まいで、屋号のロゴは「や」に◯で「まるや」、その外側を「八」と「丁」のモチーフが囲んでいる。今写真を見ても、とても美しく掃き清められていて、本当に気持ちがいい。


あまり時間もないからと、お味噌の説明は後回しに、八丁味噌を使った夕食を中庭でご馳走になった。この中庭が素晴らしい。味噌蔵に囲まれて、雨あがりの晴れた空に朧月が昇り、テーブルには真っ白なクロスがかけられて、ランプが灯る。そして味噌づくしのメニューは、お肉と白菜の味噌煮込み、大根の味噌煮込み、ハンバーグの赤ワイン味噌ソースがけ、味噌ペーストを塗って野菜とチーズを載せたオープンサンド、野菜スティックの味噌バーニャカウダソース、そしてお味噌汁。中庭でお食事をいただいていると、「愛情と優しさに包まれている」という言葉が浮かんでくる。味噌への愛、蔵への愛、味噌が美味しくする食事への愛、そしてそれを食べる人たちへの愛。
このツアーに参加するまでは、「八丁味噌」のGI (geographical indications, 地理的表示 *後述)問題に興味があり、その渦中にいる浅井社長とはどのようなやり手の方なのだろうかと勝手に想像していたのだが、作り手さんを訪問し、浅井社長と1日ご一緒してお人柄に触れ、みんなで食事を作り、まるやさんの中庭で味噌づくしディナーをいただいているうちに、そういうことはどうでもよくなって、こんなにたくさんの愛に溢れている作り手さんたちは、本物としてこれから先もたくさんの人たちに愛され続けるに違いないと確信した。

中庭を囲んで、味噌蔵が並ぶ。中庭に面して扉はない。木桶の下は土間のまま。蔵と桶と菌とお味噌は四季の移り変わりと共存している。人の背丈よりも大きい木桶の上に積まれた石は3トンで、寒い季節に扉のない蔵で石積みをするのは大変だという。それでも、辞める社員はいない。自分の誇りは給与支給の遅れや減給が一度もなかったことだと浅井社長は語る。


この日、浅井社長の車に乗せていただいて作り手さんめぐりをしたのだが、トヨタ(三河の誇り)・ホンダ(お隣浜松の誇り)の車が圧倒的に多いこの地域で、浅井社長はフォルクスワーゲン (VW) に乗られていた。ウチのクルマもVWなので、「三河でVWとは珍しいですね」と思い切って伺ってみたら、「若い時にドイツに留学して、その時VWに乗ってた」とのこと。日本ではオーガニックなんてまだほとんど考えている人がいなかった頃、ドイツのオーガニックやマクロビオティックの考え方に影響を受けたという。留学から帰国された後、輸出を積極的に手がけられた。オーガニックが見向きもされない日本ではなく、むしろ高く評価されるアメリカやヨーロッパ中心に販売先を開拓していった。八丁味噌はフランスなど海外のシェフに使われるようになり、浅井社長はMr. Hatchoと呼ばれるようになる。
その浅井社長が今手がけているのは、地元・三河産の有機大豆を使った有機八丁味噌。食の仕事は、グローバルとローカルの両面があるが、グローバルビジネスに携わった人ほどローカルの重要性に気づいているように思う。
ところで、ごちそうになった夕食にはすべて八丁味噌が使われていた。少ない水の量で仕込まれる八丁味噌、その固さゆえ「使いづらい」という声が多いのも事実。夕食では八丁味噌ペーストというものが使われていて、「八丁味噌1、みりん1、蜂蜜1の比率で作ればいい」と教えていただいた。家に帰って早速作ってみる。有機八丁味噌と、贅沢に三州三河みりんと、蜂蜜を1:1:1で。甘いのが苦手な人は、みりんと蜂蜜の分量を少し減らしてもいい。固い八丁味噌が柔らかくなって、作っておくと調味料として重宝する。




甘いお酒? 調味料? 三州三河みりん
順番が逆になったが、この日、三河調味料作り手4社ツアーの最初に向かったのが「三州三河みりん」の角谷文治郎商店さん。現在は三代目の角谷利夫社長、そのお嬢さんお二人は「角谷文治郎」(創業者であり初代。その子・二代目文治郎さんも二代目社長)から一文字づつ貰って、文子さん、治子さんという。わたしたちを迎えてくださったのは、治子さんのご主人・三角祐亮さん。聞けば、三角さんは日本を代表する経済紙の記者だったとのこと、それが治子さんと出会ってご結婚され、新聞社を辞められて縁もなかった三河の地で角谷文治郎商店に入社されたという。
経済紙の記者だっただけに、資料もばっちり、理路整然と説明してくださる。みりんは酒、と漠然と知ってはいても、原材料が正確に何なのか正直考えたこともなかったのだが、三州三河みりんの原材料は、もち米、うるち米(米麹になる)、米焼酎のみ。そしてこのもち米、うるち米、米焼酎をすべて自分で作っているという。
その比率を実物で示してくれる。左の一升瓶に入っているのは、もち米とうるち米(9:1)。ここに、米の半量の米焼酎を加え、醸造して圧搾してちょうど右の一升瓶分のみりんが出来上がる。「米一升、みりん一升」の製法をずっと守り続けている。

みりんといえば、「みりん風調味料」との比較は避けて通れない。スーパーに行けば、本みりんの半分以下の値段で「みりん風調味料」を買うことができる。みりんの製法で面白かったのは、仕込みの最初から米焼酎を使うこと。清酒の場合は、米を麹で発酵させて糖化させ、その糖を酵母が発酵させてアルコールができあがる(複発酵)が、みりんでは米の糖化だけを麹(正確には麹の酵素)に行わせて、焼酎を最初から入れることで菌が活動できない環境を作り、糖が減らないようにコントロールするのだという。だから、みりんは糖がたくさん入った焼酎で、販売にはお酒の販売免許が必要で、わたしが子どもの頃は酒屋さんで買うものだったという朧げな記憶がある。
戦時中、食糧難からお米を使った調味料の製造が禁止され、みりんの製造ができなくなった。戦後再開できたものの、贅沢品として高額の酒税がかけられた。そこで登場したのが、お米ではなく雑穀を糖化した液に化学調味料や添加物を加えた「新みりん」で、アルコールが入っていないから酒税の対象外になった。この「新みりん」、大型スーパーマーケットの登場で大量に出回るようになり、公正取引委員会により「みりん」の名称は使えなくなったが、「みりん風調味料」としてスーパーの棚の大部分を占めるようになる。
現在「本みりん」として売られている商品の中にも、水飴やアルコールを加えてのばしているものが少なくないと言う。お米1の分量に対して、角谷文治郎商店ではみりん1ができあがるが、法律上はお米1に対して2.5倍の水飴、5〜7倍の醸造アルコールを加えることが認められているという。
コストや生産効率の面から、それらの調味料が悪いとは思わないけど、昔ながらの製法で作ったみりんは「甘いお酒」であり、飲んで美味しいものだから、調味料として工業生産されたものとは別物と考えたほうがいいのかもしれない。


今回の訪問で、初めてみりんの味見をさせていただいた。お米と米焼酎だけで作ったみりんは、甘いリキュールだ。みりんは豊臣秀吉への献上品として歴史に登場し、当時は甘く濃い酒として高貴な人だけに楽しまれていたそうだが、元禄の時代には調味料として蒲焼などに使われるようになり、庶民にも手が届くようになった。今回のツアー後、わたしは時々キッチンで三州三河みりんをちょびっと炭酸で割って飲むようになった。江戸時代にも、こんなキッチンドリンカーが結構いたのではないかと妄想している。
七福醸造 – 美しい場所・美味しい調味料
「白だし」– よく耳にするものの、せっかくかつおだしをとる習慣がついたのだからと手を出さずにいた。ツアーの2軒目の訪問先は、白醤油・白だしの七福醸造さん。40年前の1978年、白だしを初めて世に出した作り手さんだ。
濃口醤油の原材料は大豆と小麦が半々なのに対し、白醤油では大豆と小麦の比率が1:9。濃口醤油では、大豆のアミノ酸と小麦の糖がメイラード反応を起こして褐色化するが、大豆が少ない白醤油では色が薄いままだという。白醤油は主に料亭など業務用に出回ることが多いそうだが、料理人から「白醤油と出汁を合わせたものが作れないか?」という一言で生まれたのが白だし。白醤油と、枕崎の本枯れ節、国産干し椎茸、北海道産昆布、三河のみりん、天日塩を合わせているとのこと。
到着早々、白だしを使ったお昼をごちそうになった。定番の出し巻き玉子から、鶏唐揚げ、炊き込みご飯、15分で漬けたというキュウリの浅漬け。わたしが最も感動したのは焼きそばで、薄いきれいな色なのに、上品だけど味はきっちり整っている。そして白だしを使ったドレッシングは、この日訪問する「ほうろく油」の菜種油と合わせている。お吸い物は白だしベースのフリーズドライで、半信半疑で食べたのだがとても美味しかった。

工場の中を見せていただくが、会う社員さんたちがみな「いらっしゃいませ!」と元気に声をかけてくださる。工場の外にも、中の設備にも「ありがとうの里」という赤い文字が書かれている。感謝の気持ちとともに、「ありがとう」という言葉自体もとても重要だという。水を使って行われたある実験では、「ありがとう」と言葉をかけ続けた水の結晶は美しい雪の花状で、「ばかやろう」と声をかけると汚い結晶になったという写真を見せていただく。
設備に対しても「ありがとう」という気持ちを込めて、毎朝1時間磨く。七福醸造の設備は、どれも新品のようにピカピカだ。使わせていただいた洗面所もとても美しかった。
okatteにしおぎでも家でも、キッチンを使ったらできるだけすぐ片付けようと心がけてはいるものの、洗ってしまうぐらいが精一杯。七福醸造さんは、毎朝きちんと設備を磨く時間を取り、それに加えて磨く日を設け、美しい環境を保つ努力をされている。今思い出すと、今回訪問した4軒の調味料作り手さんの仕事場はどこもとても気持ち良く掃除されていた。設備もとても美しかった。掃き清められた美しい環境は、自分たちが気持ち良く働いて良いものを作り出すためにとても大切なのだなと感じた。

本物は「伝統」ではなく「愛」- ほうろく屋の菜種油
碧南という、知多湾に近い地域に醸造蔵が集まっている。訪問した角谷文治郎商店、七福醸造、どちらも碧南にあった。港が近いから、江戸時代には交易も盛んだったという。醤油や味噌が江戸に届き、帰りの船で原料が届く。碧南の隣に西尾がある。昔ながらの方法で菜種油の圧搾をおこなっている「ほうろく屋」さんは、この西尾にある。
菜種油と聞くと「国盗り物語」の斎藤道三を思い出す。美濃と三河は全然違うのだろうけど、関東のわたしは「あぁこの辺りには菜種油の伝統が残っているのだな」と勝手に妄想してしまう。
菜種油。英語では canola oil(キャノーラ油)。以前使っていた大手メーカーの「キャノーラ油」が菜種油だったとは、当時は全く気付かなかった。国産の菜種(アブラナ)の自給率は0.04%、実に99.96%が輸入の菜種を使っているそうだ。
ほうろく屋の杉崎学さんは、もともとは菜種油とは縁のないご出身。オートバイや車を乗り回す、いわゆるヤンキーだったそうだ。身近なところでいじめや鬱に苦しむ若者たちを目の当たりにして、180度方向転換して、そういう人たちも含めて誰もが受け入れてもらえる体験型コミュニティづくりに取り組み始めた。その中で出会ったのが、菜種油の圧搾をおこなっていた大嶽製油所で、ご夫婦がもう廃業を決められていたところ、杉崎さんが弟子入りしてその圧搾方法を引き継がれたという。10年前のことだ。
食用植物油を選ぶなら「圧搾」を。管理栄養士の友人が教えてくれたことだ。圧搾ではないと、どのように搾るのか。溶剤抽出法と言って、薬で油を溶かし出すそうだ。杉崎さんが弟子入りした大嶽製油所は、圧搾法で菜種油を搾っている最後の一軒だった。
元気な心は、その土地で育った元気な作物から出来上がる。ご自身の体験からそう確信された杉崎さんは、菜種を栽培してくれる農家さんを探し始める。今でこそスローフードが見直されているが、当時は効率一辺倒。菜種は輸入、製造は溶剤抽出法で、たくさんの油を安く大量生産するのが当たり前だった時代。そんな中、国産の菜種を使って圧搾で作ると語ると変態扱いされ、協力してくださる農家はほとんどなかったそうだ。それでも渥美半島のNPOが栽培してくれることになり、全国を回って依頼した甲斐あって、今では栽培農家さんが増えているそうだ。
そうやって育った菜種油を、杉崎さんは大事に圧搾していく。菜種を天日干しして、選別する。最も大切な過程が焙煎。温度をあげればたくさんの量を搾れるそうだが、高温の焙煎は種と油を変質させるからと、杉崎さんは温度を上げない。焙煎について熱く語る杉崎さんを見ていたら、焙煎にこだわるコーヒー屋さんを思い出した。大嶽製油所の設備を引き継いでおり、焙煎機は昔ながらの薪で熱するタイプ。すべて手作業で大事に油を搾っている。設備は今もピカピカだ。




搾りたての菜種油の香りを嗅がせてもらう。新鮮な野菜の香りがする。「キャベツの香りがする!」と言った友人がいたが、キャベツも同じアブラナ科。杉崎さんは、種も油も生きていると言う。香りを嗅ぐと、本当に生きている油ってあるんだなと思う。
搾る工程のお話を伺っている間に、妻の和香子さんがイワシのアヒージョを作ってくださる。碧南のカネ光水産さんの丸干しイワシを、たっぷりの菜種油で。材料はそれだけ。頭から尻尾まで全て食べられる柔らかさ。絶品でした。


あとから気づいたが、伝統的な圧搾法で菜種油を作る杉崎さんから、「伝統」「伝統を守る」という言葉は全く聞かなかった。伝統を守るためにやっているのではなく、人が元気になるためにやっている。そのために、元気な材料にこだわり、その素材を活かした作り方にこだわる。菜種油の新鮮な香りを嗅ぐと、油が生きていると感じる。同時に、ごま油やオリーブオイルなど他の油も、きちんと作っている油は本当に美味しいんだろうなぁと思う。「美味しいから」だけじゃなくて、作り手さんの思いを感じられるような油を使っていきたいな。
この後、まるや八丁味噌さんに移動して、素敵な中庭で夕ご飯をご馳走になったのだが、最後にサプライズ。暗くなった中庭を、静々とバースデーケーキがやってきた。食べ物で繋がっている仲間たち、本当にあったかい。どうもありがとう!

八丁味噌のGI(geographical indications, 地理的表示)問題
大豆、麹菌、塩、水だけで仕込まれている味噌を豆味噌という。通常の味噌と違って、米麹や麦麹を使わない。水の量が少なく、出来上がった味噌は固い。水分量が少ないため、仕込みにおいては空気が入らないように固く踏み固め、桶に巨大な石積みをして重しをする。日本で豆味噌が作られているのは、愛知、岐阜、三重の東海三県。「八丁味噌」はこの豆味噌で、徳川家康公が生まれた岡崎城から西へ八丁(約870m)、旧東海道の街道筋にある二軒の味噌蔵(まるや、カクキュー)が作っている。

地理的表示とは、「農林水産物・食品等の名称であって、その名称から当該産品の産地を特定でき、産品の品質等の確立した特性が当該地域と結びついているということを特定できる名称の表示」である。(農林水産省「地理的表示法について」より)夕張メロン、前沢牛、米沢牛、市田柿のように「地名+産品名」で表示される。
八丁味噌のGI(地理的表示)問題とは、この老舗二軒の味噌蔵が加盟していない「愛知県味噌溜醤油工業協同組合」に対して農林水産省が「八丁味噌」を名乗ることを認め、結果として本家八丁味噌の二軒が「八丁味噌」を名乗れなくなってしまったというもの。
上記二社と岡崎の四大学学長などが立ち上げた「岡崎の伝統を未来につなぐ会」によれば、「八丁味噌」のGI申請と認定の経緯は以下のとおり。
平成27年6月に八丁味噌協同組合が申請、その後、愛知県の組合も申請。八丁味噌協同組合は農水省から「地域に争いのあるものは登録しない」「登録を目指すのであれば、生産地を愛知県に」「今のままでは登録は困難」と言われ、約2年農水省とやり取りしたが、拒絶の可能性が濃厚となり、やむなく平成29年6月に申請を取り下げました。
その後、愛知県の組合申請に対し岡崎市、岡崎商工会議所、八丁味噌協同組合はそれぞれ反対の意見書を出しました。しかし地域に争いがある中で、平成29年12月、わずか半年で現在の内容(筆者注:「愛知県味噌溜醤油工業協同組合」が「八丁味噌」の名称を使用する)が認定されました。
愛知県味噌溜醤油工業協同組合に対して認められた「八丁味噌」の製造方法では、老舗二社が木桶を使っているのに対しタンクの使用が可能。老舗二社の熟成は、温度管理を行わない味噌蔵での天然醸造で、期間は2年以上。対して愛知県の組合は、温度管理が可能で10ヶ月以上となっている。
みりんと「新みりん(後の「みりん風調味料」)」の話を伺って感じたのは、「新みりん」の登場にはそれなりの理由があったし需要もあったということ。ただし、それは「みりん」ではないということで「みりん風調味料」という呼び方に落ち着いた。豆味噌についても、木桶で2年かけて機械を使わずに作るとなると生産量も限られ、生産性アップのためにタンク使用や温度管理(熟成が進みやすい温度に設定)することはある意味当然だし、需要もあったのだと思う。実際、機械化が進んだ工場で作られた豆味噌で、美味しいものはたくさんあるだろう。
でも、地理的表示の面では、八丁(現在の岡崎市八帖町)という場所で江戸時代から作られている八丁味噌というものが日本で、世界で認められており、それを「八丁味噌」として他の豆味噌と区別することを認めなければ、一体何のための地理的表示制度?と思ってしまう。
とはいうものの、四軒の作り手さんを訪問し、伝統的な調味料を作りながらも、伝統を守るために作っているのではない、いいものを、美味しいものを作りたいという一心で取り組まれている皆さんのお話を伺っているうちに、GI問題はとりあえず横に置いておいて、こんなにたくさんの愛に溢れている作り手さんたちは、本物としてこれから先もたくさんの人たちに愛され続けるに違いないと確信したのだった。
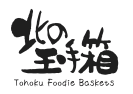

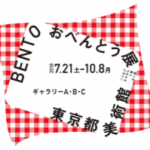

この投稿へのトラックバック
トラックバックはありません。