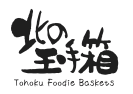バレンタインの季節に “Chocolat(ショコラ)” を読んだ
昨年からよく本を読むようになったので(決して数は多くないのですが、結構根性入れて読む本が増えた)、昨年暮れから今年はどんな本を読もうかなーと考えていました。お正月の二日に目覚めたとき、今年は『食べる本』をたくさん読もう!と思いたち、さっそく長年本棚で眠っていた Chocolat (Joanne Harris、邦題「ショコラ」)を読みました。
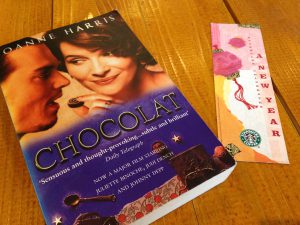
ジュリエット・ビノシュ主演の映画にもなった「ショコラ」
どうも2001、2年ぐらいに買ったらしく、ちょっと読んでほったらかしになっていたのですが、本も、挟まっていたスタバのしおりも黄ばんで年代ものの雰囲気です。その頃、以前働いていたアメリカ系の会社に転職したばかり、転職前に受験した大学院も受かったので掛け持ちでパートタイム学生をやり、とても本を読むどころではなかったんです。
この「ショコラ」、ジュリエット・ビノシュ主演の映画にもなったので、観た方もいらっしゃるのではないでしょうか。映画のレビューは「フランスの田舎町のオシャレなショコラテリを舞台にした大人のファンタジー」みたいなのが多かったけど、本はかなりシリアスです。ちなみに、この本の表紙になっているジュリエット・ビノシュ(が演じている主人公)が、ジョニー・デップ(が演じているジプシーの男性)にチョコレートを食べさせるなんて場面は出てきません。
チョコレートは頑なな心を溶かすことができるか?
イースター(復活祭)に先立つ受難節の前日、マルディ・グラのお祭りの日。ボルドーに近く、ガロンヌ川の支流が流れる小さな町に、ヴィアンヌとその小さな娘がやってきます。町の中心である教会の正面、元パン屋の物件を借りて、受難節の初日(灰の水曜日)にチョコレートショップをオープンしたことで、レイノー神父の怒りをかいます。チョコレートを快楽の象徴と考える神父は、少年時代以来チョコレートを口にしていないのです。ヴィアンヌ、神父の日記が交互に現れるという形式で、二人の独白に現れる人間洞察は実にシニカルです。200名程度の小さな町が舞台といっても、人間の姿はどこも同じ。規範に固執し、権威に固執し、人々を管理したい(本人は「導く」と考えている)神父、無神論者の老母を疎んじて体制側につき、体面を保つことに執念を燃やす母、その母親の顔色をうかがってばかりで吃りがなおらない息子、「あるべき姿」に固執して、それに反するものには躊躇せず暴力をふるい、犯罪さえもいとわない粗暴な夫、その妻はいつもびくびくしていて万引きをやめられない…。
本人たちは、実に真剣に人生を生きているのですが、その姿は滑稽でもあります。イースター(復活祭)の日にチョコレート・フェスティバルを開催しようと計画するヴィアンヌと子どもたちを阻止するために、体制側・体面固執の母親たちが撒いたビラに書かれていたプロパガンダは「イースターは、チョコレートでなく教会へ!(CHURCH, not CHOCOLATE, is the TRUE MESSAGE of EASTER! ) 」。なんと教会とチョコレートが同列なんですね。
旗色が悪くなった神父が、チョコレート・フェスティバルを阻止するためにとった最後の手段(犯罪です)の最中で、チョコレートの誘惑 (“Try me… Test me… Taste me…”)にどう対峙するのか…。
甘くない、本とチョコレート
わたしが小学生のとき、「チョコレート戦争」という本がありました。図書室で見つけて、ものすごく楽しそうな本なので嬉々として読み始めたのですが、案外シリアスな内容でした。人を浮き浮きとさせる「チョコレート」、でも人の生活には「浮き浮き」とは正反対の暗い側面がたくさんあります。そのコントラストを際立たせるのがチョコレートという存在なのでしょうか。
物語の最後、ヴィアンヌと娘がこれからどうするのかははっきりわかりません。とどまろうという気持ち、変わろうという気持ち。マルディ・グラから復活祭の翌日までのほんの49日間を描いたお話、とても豊穣な時間でした。わたしはチョコレートは食べなかったけど、ホットチョコレートを飲みながら読みました。