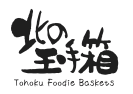田舎のパン屋が見つけた「腐る経済」
「タルマーリー」というパン屋さんがずっと気になっていました。元々は千葉県いすみ市でオープン、その後、岡山県真庭市勝山に移転。岡山市から2時間ぐらいかかる不便な場所にあるにも関わらず、自家製天然酵母のパンを求めてお客さんがはるばる訪ねるらしいのです。
ということで、タルマーリーの渡邉格さんが書かれた、『田舎のパン屋が見つけた「腐る経済」』を読んでみました。

1. 発酵について
発酵って理解するのがすごく難しいです。日本酒の酒蔵に行っても、パン職人さんの話しを聞いても、部分的にわかったような、まったくわかっていないような。生きている菌の活動である、ということを理解するというか、実感するのが難しいのだと思います。この本では、「タルマーリー」の看板商品、酒種パンの作り方をイラストや文章で説明することによって、わたしたちのまわりに存在している菌がどのような働きをしているのか教えてくれます。今まで、発酵の本をパラパラと読んでみてもチンプンカンプンだったのですが、この本を読んで、その働きが少しだけわかった気がしました。
2. 菌の働きと、「自然」「天然」「有機」の意味
菌は、食材を発酵させたり腐らせたりします。面白かったのは、なぜ「腐る」「発酵する」の差が生まれるのか、という著者の解説。十分に生命力を持った食材は、生きている菌と一緒になることによって、食べられるものに形を変える。一方、既に生命力を失った食材、自然界では存在しないような栄養過多の食材が菌と一緒になると、「これは土に還さなくてはいけない」と菌が考えて腐らせてしまう。
たとえば有機農法で栽培された穀物でも、動物性の栄養素がたくさん入っているものを麹菌と混ぜると、すごく臭いにおいを出すそうです。「植物のはずなのに、動物性の栄養素が入っているこれは変だから、腐らせてしまおう」と菌が考えているらしい。
冷蔵庫の中で、忘れていた食材が腐ってしまうことってありますが、それはその食材が生きていた証拠。腐らない食材も怖いものです。腐ることにも意味があるんだな、と思いました。
3. パン屋が見た資本主義経済
パン屋として修業する経験を通して、著者は利潤を出すとはどういうことかを理解していきます。人件費というコストに対して、より大きい労働力を得られれば、それだけたくさんの商品を作ることができます。労働時間をできるだけ長くすること、労働者の生産性をあげることによって、それは実現されます。
また、安定して大量の商品を生み出すには、気候や材料に左右されて不安定なパフォーマンスの天然菌を使うよりも、純粋培養された菌を使ったほうが生産量が安定するし、より多い生産を見込めます。それは良い面もありながら、職人の技術を喪失させてしまう面もある。職人が材料を使うのではなく、材料(イーストなど)が職人を使うことになりかねない、とも言っています。
著者は、たとえ不安定であっても天然の菌を使い、自分の技術を向上させることでパンを生産する道を選びます。そして、労働力と人件費がみあっている状態、生産者に支払う原材料費がその内容にみあったものであることを目指します。結果、著者は利潤を生まない商売を目指すことになります。
4. 「腐らない経済」とは何か。「腐る経済」とは何か。
自然界のものは、時がたてば腐ります。一方、お金は時が経っても腐らないし、資本主義経済では「どんどん増やさないといけないもの」として考えられています。腐らない経済とはどういうことか? そこでは、 資本に対してより大きい労働力を求め、より多い生産量を求めます。結果、利潤をできるだけ多く生もうとする資本家と、低い賃金で長時間働かされる労働者を生むと著者は言っています。そして彼は、その反対、つまり「腐る経済」を地方で目指す、と決めるのです。
経済の部分はマルクスの「資本論」がベースになっていて、難しいし、「お前は共産主義者か」というような内容でもあるのですが、第一次産業の生産者たちに価格決定権がない(=仕入れる大手流通が決めている)とも言われる状況、食品や飲食の低価格化がすすむ現状で、こういう側面も考えないといけないな、と思った一冊でした。